愛の歌が聴こえる by cragycloud
ぐらん、ぐらんと頭の中で渦が巻いているような感じがしていた。僅かに目を開けてみたが、焦点が合わずに周囲がぼやけて見えた。少し時間がかかったが、だんだんと周りの様子が見えてきた。見覚えのあるソファーやカーテン、テーブルがあった。なんのことはない、ここは自分が住むマンションのリビングであった。
どうやらリビングの床にうつ伏せで倒れていたらしい。右の頬骨あたりに少し痛みがある。赤く腫れ上がっているかもしれないなと思いながら、床に手をついて起き上がろうとした。しかし、体が重く感じてふらついた。
そのときはっとした。何故か、手は赤い色で染まっていたからだ。とくに右手は赤いペンキに手を突っ込んだように手首まで真っ赤だった。しかも、それは鮮明な赤ではなかった。もっと特別な赤であった。間違いなく血だった。何故?、という疑問と不安が過っていた。
自分の体を確認してみたが、どこも怪我はしていないようだ。だったら、この手の血はなんだ。いや手だけではない、シャツも腹部の辺りが赤く染まっていた。不安を覚えながらも、とにかく手を洗おうと洗面台に行こうとした。しかし、手だけでなく体も洗って、それから着替えようと思い直して風呂場に向かった。
シャワーを浴びると赤い血はみるみる流れて排水溝に吸い込まれていった。着替えをしてから、疑問と不安を解消するために部屋の中を確認した。リビングの床には血の跡が残っている。後で拭かなければと思いつつ、別の部屋も見たがとくに異常はなかった。しかし、寝室は何故か見なかった。
やれやれと思いながら、リビングの血の跡を拭き掃除しているとピンポーンと来訪を知らせるチャイムが鳴った。誰だろうと思って、しばらくのあいだ様子をみた。そのとき、ガチャと言う音がして誰かが部屋に入ってきた。
「ごめーん、遅くなって。ごはん食べたー」
と言って入ってきたのは妻であった。時刻は、もうすぐ深夜の午前1時になろうとしていた。
「お腹すいたー、ごはん作るね、一緒にたべよ」
「えっ、もう1時も過ぎたよ。これから作るの」
「そうよ、だって作りたいから。それに健康にいいでしょ」
「ま、そうだね。つき合うよ」
「そう、よかった」
妻は、美容師をしている。いや、それを言うと嫌がる。なんでも、ヘアースタイリストというのが正式名称らしい。結婚して約3年が経っていた。最近では、お互い慣れたというか、むしろ倦怠期になっていた。自分はサラリーマンで休日は土曜と日曜だ。彼女はというと、平日が休日であった。
仕事柄それは仕方がないことであった。それでも結婚当初は、自分が有給を取って彼女の休日を共に過ごした。しかし、それも長くは続かなかった。
「ねー、一緒に家で食事するのは久しぶりじゃない」
彼女は、着替えもせずにキッチンで何かをしながらそう言った。
「そうだね、お互い忙しいから仕方がないよね」
「たまには食事ぐらい一緒にしたほうが良くない?夫婦だし」
「それは、そうだけど。でも・・・」
妻と知り合ったのは、彼女の勤める美容室であった。知り合いの紹介で行ったのである。その美容室は原宿の神宮前交差点からほど近く、ラフォーレの裏側辺りにある細い小径をしばらく行った先にあった。とても洒落た造りの美容室で、その分値段も高かった。
最初から彼女が気になっていた。そこで何回目かに行ったときに彼女を指名した。彼女は、知らない自分に気さくに話しかけてくれた。もっとも、それも商売のうちということではあったが。それからは、約2ヶ月に一回は通うようになっていた。もちろん、担当は彼女であったのは言うまでもない。
何ヶ月かした後に、思い切ってデートに誘ってみた。幸い、そのとき彼女には特定の彼氏がいなかった。そして、いつのまにか恋人どうしになっていた。それからは、有給を取ってテーマパークや温泉にも行った。ほとんどのデートは彼女の都合に合わせていた。そして、初めて会ってから1年ほどで結婚していた。
それから、約3年が経っていた。彼女はきれいでスタイルも良くて、お洒落である。誰でもがいい女と思うだろう。そんな彼女と結婚したのは、自分ながら誇らしくもあった。しかし、時を経て徐々に隙間ができてきた。それは、休日を一緒に過ごす事がないことも原因であった。夫婦とはいえ、顔を合わせるのは朝と夜のほんの少しの時間だけとなっていた。
彼女は忙しくなっていた。美容室の仕事だけでなく、芸能人のヘアーメイクの仕事もするようになっていたからだ。彼女の料理をもう一年以上食べていなかった。
「どう、おいしい?」まるでフランス料理みたいに盛りつけた料理を食べながら彼女は言った。
「おいしいね。こんなに料理うまかったんだ」
「あれ、いつもはおいしくなかったんだ」
何かおかしいと感じた。彼女はいまでは料理は作らない。たしかに結婚当初は、凝った料理を作ったりしたが、こんなにうまかった記憶がなかった。
「このお皿お洒落でしょ」
「うん、こんなのあったけ」
「いやだー、結婚したときに揃えたのよ。忘れたの」
「いや、そうだったか。ごめん」
「ま、許すよ。おいしいと言ってくれたから。ねー、今度大阪の、そうUSJいかない」
「んっ・・・いいね」
真夜中の食事が終わって片付けを手伝った。彼女は、これからシャワーを浴びるという。それじゃ、自分はそのあいだにビールでも飲むかと冷蔵庫の扉を開けた。そのとき、冷蔵庫の冷気が顔をひんやりと霞めていった。
時刻は、午前2時を過ぎていた。ビールを飲みながら考え事をした。それは、思い出したことがあったからだ。今日の彼女は優しかった。それも尋常ではない優しさであった。何故なら、彼女は離婚を切り出していたからだ。
彼女は、きれいでスタイルもいいが、自分本位で気も強かった。結婚前はそれも個性と思って可愛く思えた。しかし、結婚してからは、可愛い部分はどこかに消えてしまった。ときに、自分の主張だけを押し通そうとする彼女に辟易したこともあった。
そんな彼女が、離婚を切り出したのだ。これは、もう決断したとしか思えなかった。ところが、今日はどうしたのか。何か、変だとしか思えない。それを思うと彼女に何か心境の変化があったのか聞きたくなった。
彼女は、まだシャワーから出てこないが、構わずに風呂場のドアを開けた。
しかし、そこに彼女はいなかった。脱いだはずの洋服さえなかった。風呂場のなかにもいなかった。シャワーを使った形跡もなかった。どこにいったのか。そう思って、そう広くもないマンションの部屋を確認した。しかし、どこにもいない。
そうか、寝室だ。寝室はまだ見ていなかった。思えば、寝室は何故か見ない振りをしていた。何故だろうかと疑問になったが、それを深く考える事なく寝室のドアを開けて中に入った。そのあと、ドアは何故か音も無く閉まっていた。
寝室の中は何故か、淀んだ空気が漂っている、そんな気がしていた。それに何か変な匂いもしている。これまでに経験したことがない匂いであった。それに冷気を感じた。暗いのでドアの脇にあるライトのスイッチを入れた。そして目にしたものは想像を超えていた。
見慣れたベッドには何かがいた。それは妻であった。しかし、ぴくりともしないようだ。それも当たり前であった。彼女の腹部辺りに包丁が刺さったままであった。その周囲は血が滴っていた。ベッドもほぼ赤く染まっていた。
それを目にした自分は、記憶が蘇ってきた。自分が妻を刺したことを。なんてことをしたんだと思っても、もうどうしようもないことであった。そのとき、何かを叩く音がした。
それは、「トン、トン」と寝室のドアを外側から叩く音だった。「誰だー」と叫んだ。しかし、返事はない。するとまた音がした。
「トン、トン」・・・「トン、トン」・・・とそれは続いた。
時刻は、午前3時を過ぎていた。
(おわり)
アイキャッチ画像:以下のサイトより
名古屋綜合美容専門学校 shingakunet.com
美容師として働く柴田絵梨さん
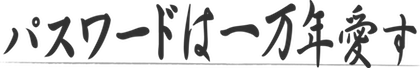



コメント